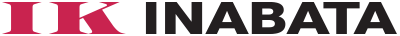- 方針・基本的な考え方
- 目標
- 体制(ガバナンス)
- 化学品規制管理
- 廃棄物管理・リサイクル推進
- イニシアティブへの参画
- 主な取り組み:乾式オフィス製紙機「PaperLab」の導入
- 主な取り組み:ごみの分別
- マテリアルリサイクルビジネス
方針・基本的な考え方
稲畑産業グループは、大気・水・土壌の汚染予防、有害廃棄物・汚染物質の排出削減および適正処理、適切な化学物質管理等を通じて、人の健康や環境への悪影響の最小化に努めています。
また、持続可能な資源の利用や使用する資源の最小化、廃棄物の削減、リサイクルの推進等を通じて、資源循環に努めています。
マテリアリティにおいても「脱炭素社会・循環型社会への貢献/自然資本の持続可能な利活用」を掲げており、事業を通じたサーキュラー・エコノミーの実現にも注力しています。
目標
「サステナビリティ中期計画2026」の中で、戦略およびKPI・目標を定めました。
| 戦略 | KPI・目標(2024年4月~2027年3月) | バウンダリー |
|---|---|---|
|
化学物質規制管理の強化による 安全・安心な品質の確保 |
国内外における化学物質規制の動向をタイムリーに把握・共有し、管理体制を強化 | 連結 |
2024年度の取り組み
目標達成に向け、2024年度は以下4つの取り組みを実施しました。
| 取り組み | 概要 | |
|---|---|---|
| 1 | 世界の化学品規制情報を定期的 (月1回)に全社へ配信 |
化学品規制管理部で収集したグローバルな化学品規制動向に関する情報を、海外グループ会社を含む全社に共有しています。 これにより、従業員の化学品規制に関するリテラシーを高めるとともに、取扱商品に関する新しい規制への適切な対応を促し、コンプライアンスを維持向上することを目的としています。 |
| 2 | グローバルな化学品規制管理体制の構築と、化学品規制検索システムの活用推進 |
国内外グループ会社に化学品規制管理担当者を配置し、各拠点が独自に各国の法令対応を行う体制を整備しました。 またグローバルな化学品規制検索システムを導入し、各拠点の担当者は本システムを活用して商品輸入開始前の法規制確認などが可能となっています。 |
| 3 | 国内外グループ会社に対する化学品規制対応状況の確認と支援 | 各グループ会社との定期面談を通じて、整備した化学品規制管理体制の運用状況の確認と支援を行いました。 |
| 4 | 社内セミナーの実施 | 社外の専門家による、サーキュラーエコノミーに関する世界動向とリサイクル樹脂の化学物質管理に関するセミナーを開催しました。25年度も別テーマで開催予定です。 |
化学品規制管理
基本的な考え方
ケミカル事業を中心に4つの事業を展開する当社グループにとって、法規制に則った適切な化学品・化学物質の管理は重要な課題です。化学物質は非常に有用なものである一方、水・土壌・大気や動植物の生態系といった地球環境や人々の安全と健康に悪影響を及ぼすことがあります。そのため、製造・販売・輸送・保管等の様々な場面において、数多くの関連法規制があり、取り扱いにおいて許認可を要するものもあります。これらに適切に対応しなければ、ケミカル事業や経営そのものに重大な悪影響を与えることにもなりかねません。そのため、ますます強化される国内外の法規制動向をしっかりと認識し、適切に対応していきます。
また、各営業本部の個別案件については、化学物質に関する環境や社会への影響を事前に評価し、十分な対策を講じた上で新規事業を推進しています。
体制
当社の管理本部に化学品規制管理の専門部署を設け、国内外のグループ会社を含めた化学品規制管理体制の整備を進めています。
目標
化学品に関する世界の法規制への対応
化学物質の製造と使用による人の健康と環境への悪影響の最小化を目指す「国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ(SAICM)」およびSAICMの後継となる「化学物質に関するグローバル枠組み(GFC)」に基づき、世界各国で化学品法規制が新たに制定・改正されています。SAICM/GFCに基づいた対応を行うため、当社グループは日本国内だけでなく海外現地法人における化学品法規制管理の体制構築を進め、海外法規制の調査システムの導入・活用や、各国の法規制に合わせた運用のルール化を実施するなど、関連する各国・地域の法規制に対応しています。
国内においては、化学物質審査規制法(化審法)、労働安全衛生法(安衛法)、化学物質排出把握管理促進法(化管法)、毒物及び劇物取締法(毒劇法)、消防法等、多岐にわたる関連法令を遵守しています。また、法令に基づいた許認可の管理も徹底しています。
■各国動向の一例
| 地域・国 | インベントリ | GHS* |
|---|---|---|
| 日本 | 化学物質審査規制法 | 労働安全衛生法 |
| 米国 | TSCA | HCS(OSHA) |
| EU | REACH | CLP |
| 中国 | 新化学物質環境管理弁法 | 危険化学品安全管理条例 |
| 韓国 | 化評法(K-REACH) | 産業安全保健法 |
*GHS:化学品の分類および表示に関する世界調和システム(The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)とは、化学品の危険有害性(ハザード)ごとに分類基準及びラベルや安全データシートの内容を調和させ、世界的に統一されたルールとして提供するもの。GHSは2003年7月に国際連合から勧告され、その後定期的な更新が行われている。日本を含め各国で、化学品の分類や表示についてGHSを導入して行っている。
■稲畑産業で保有する業許可・品目許可一覧
医薬品製造業(包装・表示・保管)/医薬品卸売販売業/化粧品製造業(包装・表示・保管)/農薬販売業/肥料販売業/飼料輸入業/飼料販売業/麻薬等原料輸出業者/麻薬等原料輸入業者/特定麻薬等原料卸小売業者/動物用医薬品卸売販売業/高度管理医療機器販売業/第一種高圧ガス販売業/第二種高圧ガス販売業/毒物劇物一般販売業/毒物劇物輸入業/内装仕上工事業/機械器具設置工事業/建築工事業/古物商/アルコール販売事業/酒類販売業
化学品の安全管理に対する自主的取り組み
当社では、取り扱う化学品を安全に管理するために、「輸入化学商品管理規則」「労働安全衛生法に基づく社内化学物質規則」などの社内規程を整備し、法規制に基づく適切な運用を行っています。
従来から、取り扱い化学品に関する法規制情報を商品マスタ管理システムに登録し、一元管理を行ってきましたが、2023年度に実施したグローバル基幹システムの刷新に伴い、これらの管理についても更なる強化を行いました。商品マスタに成分情報をデータとして登録し、商品毎の最新の法規制情報が管理できるような運用に更新しました。これにより、年々新たに追加される法規制対象物質について、タイムリーな法令対応が可能となりました。同システムを導入している国内外のグループ会社についても、同様の運用を行っています。
また、関連団体に加盟して化学品規制に関する最新情報を入手しています。
なお、当社をはじめ一部の国内外グループ会社においては、環境マネジメントに関する認証(ISO14001)や品質マネジメントに関する認証(ISO9001)を取得しています。
化学物質情報の提供/登録
取り扱う商品を安全に管理するために、化学物質情報を川上から川下へ途切れさせることなく、適切に情報伝達していくことは、サプライチェーンを支える商社としての重要な役割だと考えています。化学物質管理者の元、サプライヤーが発行するSDS(Safety
Data
Sheet:安全データシート)の最新版を入手し、上述のシステムの中で適切に管理するとともに、当社が輸入者として発行するSDSについても、手順を定めて漏れのないように定期的な改訂を行っています。顧客へのSDSの提供を通じ、化学物質の危険有害性情報や安全な取り扱い方法を伝達することにより、化学物質に起因する職業性疾病の発症や産業活動に伴う環境汚染を防止できると認識しています。加えて、当社は商社であり最終製品を製造する立場ではありませんが、化学物質情報をサプライチェーンで適切に伝達していくことは、最終的には消費者の意識向上にも役立つと考えています。
また、欧州の化学品規制のREACH規則や米国TSCAに対応して、対象となる化学物質の登録を適切に行っています。
懸念化学物質の段階的な削減・代替
健康や環境に悪影響を与える恐れが懸念される化学物質の段階的な削減・代替は重要な課題であると認識し、対応を進めています。当社では、POPs条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)*や関連する各国法に基づき、特定の有害化学物質の使用削減や代替を進めています。例えば、商社である当社において輸出入業務は主要な業務ですが、POPs条約で付属書A(廃絶対象物質)に追加された化学物質を含む化学商品の輸出入におきましては、各国の規定に従った取引を徹底しています。
また、物質の化学構造や各国のリスク評価の動向などから将来的な使用の継続性が懸念される物質については、化学品規制管理の専門部署が定常的に情報把握に努め、社内研修などを通じて社員に周知するとともに、営業部門による顧客要求の把握や代替品の情報収集などの対応を進めています。
具体的な活動の一例として、HFC(ハイドロフルオロカーボン)の段階的な削減・代替があります。1987年、国際条約であるモントリオール議定書が採択され、CFC(クロロフルオロカーボン)がオゾン層を破壊する物質の一つとして使用が規制されました。CFCの代替品としてHFCが使用されていましたが、HFCは温室効果ガスとしての性質を有することから、2016年の同議定書キガリ改正によってHFCも段階的に削減することが決定されました。当社の顧客においても主に発泡剤としてHFCを使用していましたが、キガリ改正を受け、代替品であるHFO(ハイドロフルオロオレフィン)の取り扱いを推進しました。
*環境中での残留性、生物蓄積性、人や生物への毒性が高く、長距離移動性が懸念されるポリ塩化ビフェニル(PCB)、DDT等の残留性有機汚染物質(POPs :Persistent Organic Pollutants)の、製造及び使用の廃絶・制限、排出の削減、これらの物質を含む廃棄物等の適正処理等を規定している条約
社内教育の実施
組織としての管理体制の強化とともに、化学品を取り扱う社員一人ひとりが正確な知識を習得し、運用フローを徹底することが重要と考えています。法令改正時の全社研修や階層別・職種別の法規制研修などを行い、重要なテーマについては出席を必須としています。さらに、任意参加の化学品法規制基礎研修や世界の化学品法規制動向セミナーなども定期的に実施し、毎回多くの関係者が自発的に受講しています。
また、社内ポータルサイトに化学品規制管理サイトを設け、商品管理のフローチャートや国内外の法規制情報、各種マニュアル・申請書類などを掲載し、社員が必要な時に必要な情報を速やかに参照できるように整備しているほか、月に一度、化学品規制管理の専門部署から全社員に向けて、国内外の化学品法規制に関するニュースをメールで配信しています。
このように様々な手法を組み合わせて、化学物質の適正な管理について社内浸透を図っています。
廃棄物管理・リサイクル推進
環境マネジメントシステムの下、廃棄物処理法をはじめとする各種法令を遵守するとともに、事業活動によって発生する廃棄物の排出量削減とリサイクルの推進に取り組んでいます。
廃棄物の不適正処理への対応として、定期的に実施している環境監査により廃棄物処理法の遵守状況を確認するとともに、電子マニフェストを導入しています。
オフィスにおいては、ゴミ分別徹底、オフィス製紙機の導入、ペーパーレス化などを推進しています。また、廃棄物処理の外部委託に際しては、可能な限り、リサイクルを行っている業者を選定しています。
イニシアティブへの参画
イニシアティブに参画し、様々なステークホルダーと協働して、サーキュラー・エコノミーの実現に向けた取り組みを推進しています。
主な取り組み:乾式オフィス製紙機「PaperLab」の導入
2019年から乾式(水を使わない)オフィス製紙機「PaperLab」を導入しています。社内の使用済みコピー紙を原料に、オフィス内で紙を再生することができます。自社での紙の再生率を上げることで、廃棄物の削減に努めています。

主な取り組み:ごみの分別
オフィスで出る様々なゴミはそのまま捨ててしまうと廃棄物ですが、適切に分別し、リサイクルすることで、再度資源として生まれ変わります。稲畑産業では、オフィスでのごみ分別を積極的に行い、廃棄物を削減し、リサイクルを進めています。
主な分別の種類
- 機密書類処理ボックス
- 上質紙/雑紙/雑誌・パンフレット
- カン/ビン/ペットボトル
- 紙コップ
- 廃プラスチック類
- 燃えるごみ