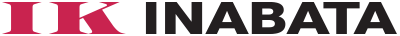2024年5月、当社グループにとって初となる「サステナビリティ中期計画2026」を策定しました。本計画は、2024年度からスタートした中期経営計画NC2026における「経営基盤戦略」の1つとして位置づけられています。
当社グループのマテリアリティに対処するべく、当社グループのサステナビリティに関する考え方を改めて明文化したほか、マテリアリティに関わるリスク・機会と主な取り組みを整理し、長期的なビジョン、戦略及びKPI・目標を掲げました。
稲畑産業グループのサステナビリティ
稲畑産業グループは、経営理念『「愛」「敬」の精神に基づき、人を尊重し、社会の発展に貢献する』を掲げ、信頼を礎とする人間尊重の経営を続けてまいりました。この「人」と「社会」を大切にする思想は、今日、世界が目指す「持続可能な社会の実現」に貢献しうるものだと考えています。
ここ数年で、サステナブルな企業経営を求める社会的な風潮は、明らかに加速しています。環境保全、人権の尊重、社員の労働環境への配慮、公正な取引など、解決すべき社会課題は山積しており、これら社会課題の解決に対して、ビジネスセクターである企業への期待が高まっていることへの証であると認識しています。
これらの社会課題は、今後の企業活動において大きなリスクとなる一方で、適切な対応を先んじて選択していくことで、当社グループの持続的な成長への大いなる機会になると考えています。そのため、サステナビリティを重要な経営課題として取り組んでいます。
商社である我々は、創業から130年超にわたり、日々変化する顧客の課題を顧客の立場から解決し、バリューチェーンをより良い形でつなぐ、という役割を果たしてきました。時代ごとの社会変化に俊敏に対応し、顧客や社会のニーズに貢献するという当社グループの姿勢は、先行きが不透明で将来の予測が困難なこれからの時代において、リスクと機会を考慮した価値の提供により、これまで以上に重要な役割になれると考えています。
時代を超えて社会から必要とされる商社であるために、あらゆる事業活動を通じて、長期的な企業価値向上と持続可能な社会の実現を目指してまいります。
マテリアリティ・解説と関連セグメント
| マテリアリティ | 主な内容 | |
|---|---|---|
| 持続的な 価値創出 |
脱炭素社会・循環型社会への貢献 /自然資本の持続可能な利活用 |
脱炭素社会・循環型社会の実現に向けて、再生可能エネルギー関連や代替燃料関連、リサイクル関連、EV関連等の環境関連ビジネスに注力していきます。また、建材関連や食品関連等のビジネスを通じて、自然資本の持続可能な利活用を進めていきます。地球環境保全の観点では環境マネジメントシステムを土台として、GHG排出量削減や廃棄物削減・資源循環、汚染防止、水資源・生物多様性の保全等の取り組みも推進していきます。 |
| 安全・安心で豊かな生活への貢献 | 生活に関わるモビリティ関連や食品関連、ライフサイエンス関連のビジネスを中心として、暮らしの様々な課題を解決し、人々が安全・安心に豊かな生活を送れる社会の実現に貢献するビジネスを提供していきます。あらゆる産業の土台となるケミカル製品を取り扱う上での責務である化学物質管理や製品安全、品質に関しても高い意識を持って取り組んでいきます。 | |
| レジリエントな調達・供給機能を通じた価値提供 | 柔軟で最適な取引を継続的に提供することは、商社である当社グループの重要な機能です。不確実性が高く、未来が予測しにくい社会において、変化する顧客や社会のニーズに応え、課題解決に貢献する当社グループの機能は、その価値をより発揮します。グローバルなネットワークを活かし、商材開発・パートナー開拓・物流ノウハウといった複合的な商社機能を駆使して、サプライチェーンマネジメントを強化し、レジリエントな調達・供給機能を通じて価値を提供していきます。 | |
| 事業継続の基盤 | 「愛」「敬」の精神に基づく人権尊重と地域社会との共生 | 社是である「愛」「敬」という人間尊重の精神に基づき、当社グループの企業活動に関連するステークホルダーの人権を尊重します。また、事業を展開する世界各地の人々と価値を共有し、地域社会とそこに暮らす人々と共に発展することを目指します。 |
| 価値創造を担う人的資本の育成・強化 | 新たな価値を創造する社員は、当社グループにとって最大の財産です。高い倫理観と熱い志を持ち、グローバルな視野で課題解決に臨み、信頼される顧客のベストパートナーになる。そのような魅力のある「人間力」の高い人財が、持続的な価値を生み出す源泉です。それぞれの多様性を認め合い、自由闊達な議論とチームワークを重んじる組織風土が、社員の満足度を高め、社員と当社の持続的な成長につながるものと考えます。新たな働き方改革やダイバーシティ&インクルージョン、従業員エンゲージメント、人財育成・能力開発、労働安全衛生等の取り組みを進めていきます。 | |
| ガバナンス・リスクマネジメントの強化 | 持続的に企業価値を向上させるため、経営の透明性・公正性を確保し、迅速・果断な意思決定をおこなう基盤となる強固なコーポレート・ガバナンス体制を構築します。また、国内外のグループガバナンスを強化するとともに、コンプライアンスや腐敗防止、事業継続マネジメント、情報セキュリティ等を含むリスクマネジメントを強化していきます。 | |
「持続的な価値創出」のマテリアリティには、注力していく事業分野を掲げています。それらとセグメントとの関連については以下の通りです。
| 情報電子 | 化学品 | 生活産業 | 合成樹脂 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持続的な 価値創出 |
脱炭素社会・循環型社会への貢献 | 再生可能エネルギー関連 | ★ | ★ | ||
| 代替燃料関連 | ★ | |||||
| リサイクル関連 | ★ | ★ | ★ | |||
| EV関連 | ★ | ★ | ★ | |||
| 自然資本の持続可能な利活用 | 建材関連 | ★ | ||||
| 食品関連 | ★ | |||||
| 安全・安心で豊かな生活への貢献 | モビリティ関連 | ★ | ★ | ★ | ||
| 食品関連 | ★ | ★ | ||||
| ライフサイエンス関連 | ★ | |||||
マテリアリティに関わるリスク・機会と主な取り組み
各マテリアリティごとのリスクと機会、それらを踏まえた主な取り組みは以下の通りです。
※「持続的な価値創出」、「事業継続の基盤」をそれぞれクリックしてご覧ください。
脱炭素社会・循環型社会への貢献/自然資本の持続可能な利活用
リスク
-
気候変動関連の政策・法規制の強化に伴うコストの増加
-
石油由来プラスチックに対する政策・法規制の強化や消費者ニーズの低下に伴う収益の悪化
-
気候変動の影響による農産品・水産品の産地・収穫量・質等の変化での収益の悪化
-
気候変動や自然資本に関わる不十分な情報開示によるレピュテーションの低下、サプライチェーンからの除外
-
異常気象の激甚化による自社拠点の被災やサプライチェーンの寸断
-
グリーンウォッシュによるレピュテーションの低下
機会
-
再生可能エネルギーや電池関連の需要拡大
-
温暖化の進行に伴う企業・消費者の行動変化による適応商材の需要拡大
-
バイオマス・リサイクルプラスチック、生分解性プラスチック等の需要拡大
-
持続可能な農産品・水産品に対する需要拡大
-
環境活動の着実な推進と適切な情報開示における企業評価の向上
主な取り組み
リスク対応
機会対応
カーボンニュートラルに向けたGHG排出量削減活動の推進
◎
◎
再生可能エネルギーの導入
◎
◎
TCFDをはじめとする適切な情報開示
○
○
環境関連ビジネス(クリーンテック等)の拡販
◎
サステナビリティ関連認証の取得
○
BCPの策定・見直し、運用
○
○
サプライヤー・委託先の多様化、在庫の分散化
◎
◎
安全・安心で豊かな生活への貢献
リスク
-
化学物質関連の政策・法規制の強化に伴うコストの増加、サプライチェーンからの除外
-
製造拠点における製品安全・品質に関する規制の強化に関わるコストの増加
-
商社業での製品安全・品質に関わる対策や情報管理が不十分なことによるサプライチェーンからの除外
-
製造拠点における環境面等での地域社会・住民に対する不適切な対応によるレピュテーションの低下、訴訟リスクの増大
機会
-
消費者ニーズの変化による安全で安心な食品関連事業の需要拡大
-
感染症等およびその予防の広がりによるライフサイエンス事業の需要拡大
-
モビリティ関連事業における環境・社会面に配慮した部材等の需要拡大
-
取り扱い商材は最終的にはコンシューマーに提供されるという認識に基づき、安全・安心に関わる情報をバリューチェーンで適切に開示・共有することによるレピュテーション・信頼性の向上
主な取り組み
リスク対応
機会対応
化学物質規制管理の強化
◎
◎
商社としての製品安全・品質の管理、対策の強化
○
○
サプライチェーン・バリューチェーン管理の強化
◎
◎
食品関連事業の拡充
◎
ライフサイエンス関連事業の拡充
◎
モビリティ関連事業の拡充
◎
レジリエントな調達・供給機能を通じた価値提供
リスク
-
自然災害や感染症等によるサプライチェーンの分断
-
地政学リスクによるサプライチェーンの分断
-
在庫・輸送・委託先管理の不十分な対策によるサプライチェーンの分断
-
責任ある鉱物調達への不十分な対応によるレピュテーションの低下、サプライチェーンからの除外
-
サプライチェーン上の人権リスクに対する不十分な対策によるレピュテーションの低下、サプライチェーンからの除外
-
GHG排出量の算定(スコープ1,2,3)および削減に対する不十分な対策によるレピュテーションの低下、サプライチェーンからの除外
機会
-
地政学や環境・社会等のグローバルリスクに適切に対処し、顧客のサプライチェーンにおける最適解を提供することによる販売機会増
-
在庫・輸送・委託先の管理が行き届いたサプライチェーン構築による提供価値の向上
-
適切なBCPの策定・運用によるレジリエントな事業活動の提供
-
GHG排出量をはじめとする適切な情報開示による取引先からの信頼性向上
主な取り組み
リスク対応
機会対応
地政学や環境・社会等のグローバルリスクを考慮したサプライチェーンマネジメントの強化
◎
◎
BCPの策定・見直し、運用
○
○
サプライヤー・委託先の多様化、在庫の分散化
◎
◎
適切な情報開示、アンケート等の取引先要請への対応
○
○
サプライチェーン上の人権DDの実施
◎
◎
責任ある鉱物調達への対応
◎
◎
リスク
- 気候変動関連の政策・法規制の強化に伴うコストの増加
- 石油由来プラスチックに対する政策・法規制の強化や消費者ニーズの低下に伴う収益の悪化
- 気候変動の影響による農産品・水産品の産地・収穫量・質等の変化での収益の悪化
- 気候変動や自然資本に関わる不十分な情報開示によるレピュテーションの低下、サプライチェーンからの除外
- 異常気象の激甚化による自社拠点の被災やサプライチェーンの寸断
- グリーンウォッシュによるレピュテーションの低下
機会
- 再生可能エネルギーや電池関連の需要拡大
- 温暖化の進行に伴う企業・消費者の行動変化による適応商材の需要拡大
- バイオマス・リサイクルプラスチック、生分解性プラスチック等の需要拡大
- 持続可能な農産品・水産品に対する需要拡大
- 環境活動の着実な推進と適切な情報開示における企業評価の向上
| 主な取り組み | リスク対応 | 機会対応 |
|---|---|---|
| カーボンニュートラルに向けたGHG排出量削減活動の推進 | ◎ | ◎ |
| 再生可能エネルギーの導入 | ◎ | ◎ |
| TCFDをはじめとする適切な情報開示 | ○ | ○ |
| 環境関連ビジネス(クリーンテック等)の拡販 | ◎ | |
| サステナビリティ関連認証の取得 | ○ | |
| BCPの策定・見直し、運用 | ○ | ○ |
| サプライヤー・委託先の多様化、在庫の分散化 | ◎ | ◎ |
リスク
- 化学物質関連の政策・法規制の強化に伴うコストの増加、サプライチェーンからの除外
- 製造拠点における製品安全・品質に関する規制の強化に関わるコストの増加
- 商社業での製品安全・品質に関わる対策や情報管理が不十分なことによるサプライチェーンからの除外
- 製造拠点における環境面等での地域社会・住民に対する不適切な対応によるレピュテーションの低下、訴訟リスクの増大
機会
- 消費者ニーズの変化による安全で安心な食品関連事業の需要拡大
- 感染症等およびその予防の広がりによるライフサイエンス事業の需要拡大
- モビリティ関連事業における環境・社会面に配慮した部材等の需要拡大
- 取り扱い商材は最終的にはコンシューマーに提供されるという認識に基づき、安全・安心に関わる情報をバリューチェーンで適切に開示・共有することによるレピュテーション・信頼性の向上
| 主な取り組み | リスク対応 | 機会対応 |
|---|---|---|
| 化学物質規制管理の強化 | ◎ | ◎ |
| 商社としての製品安全・品質の管理、対策の強化 | ○ | ○ |
| サプライチェーン・バリューチェーン管理の強化 | ◎ | ◎ |
| 食品関連事業の拡充 | ◎ | |
| ライフサイエンス関連事業の拡充 | ◎ | |
| モビリティ関連事業の拡充 | ◎ |
リスク
- 自然災害や感染症等によるサプライチェーンの分断
- 地政学リスクによるサプライチェーンの分断
- 在庫・輸送・委託先管理の不十分な対策によるサプライチェーンの分断
- 責任ある鉱物調達への不十分な対応によるレピュテーションの低下、サプライチェーンからの除外
- サプライチェーン上の人権リスクに対する不十分な対策によるレピュテーションの低下、サプライチェーンからの除外
- GHG排出量の算定(スコープ1,2,3)および削減に対する不十分な対策によるレピュテーションの低下、サプライチェーンからの除外
機会
- 地政学や環境・社会等のグローバルリスクに適切に対処し、顧客のサプライチェーンにおける最適解を提供することによる販売機会増
- 在庫・輸送・委託先の管理が行き届いたサプライチェーン構築による提供価値の向上
- 適切なBCPの策定・運用によるレジリエントな事業活動の提供
- GHG排出量をはじめとする適切な情報開示による取引先からの信頼性向上
| 主な取り組み | リスク対応 | 機会対応 |
|---|---|---|
| 地政学や環境・社会等のグローバルリスクを考慮したサプライチェーンマネジメントの強化 | ◎ | ◎ |
| BCPの策定・見直し、運用 | ○ | ○ |
| サプライヤー・委託先の多様化、在庫の分散化 | ◎ | ◎ |
| 適切な情報開示、アンケート等の取引先要請への対応 | ○ | ○ |
| サプライチェーン上の人権DDの実施 | ◎ | ◎ |
| 責任ある鉱物調達への対応 | ◎ | ◎ |
「愛」「敬」の精神に基づく人権尊重と地域社会との共生
リスク
-
自社・グループ会社における人権侵害による訴訟のリスク、レピュテーションの低下、生産性の低下
-
拠点等の地域社会における人権侵害による訴訟のリスク、レピュテーションの低下
-
地域社会からの反発による操業の停止、レピュテーションの低下、就業者の不足
-
地域社会の衰退による経済の縮小、就業者の不足、治安の悪化等による操業の停滞・停止
機会
-
人権尊重の企業姿勢・行動によるレピュテーションの向上
-
自社・グループ会社における人権尊重による職場の活性化、生産性の向上
-
地域社会との共生、信頼関係の構築によるスムーズな事業運営
主な取り組み
リスク対応
機会対応
自社・グループ内の人権DD実施(人権DDデジタルサーベイ)
◎
◎
自社・グループ内の企業理念の浸透、人権に関する教育の実施
◎
◎
コンプライアンス・腐敗防止の強化
◎
○
内部通報制度の周知徹底
◎
○
外部ステークホルダーとのエンゲージメント機会の整備
○
○
社会貢献活動の推進
○
○
価値創造を担う人的資本の育成・強化
リスク
-
従業員のwell-being(身体的・精神的・社会的に満足な状態)低下による生産性や競争力の低下
-
従業員のスキル・能力の低下による生産性や競争力の低下
-
多様性の欠如による思い込み・判断ミスの発生、競争力低下
-
心理的安全性が低く、働きづらい職場環境による生産性やレピュテーションの低下、離職者の増加
-
ダイバーシティ&インクルージョンに関わる様々な制度設計、情報発信、社会的な企業評価等の不足による優秀な人材の獲得機会の喪失
機会
-
従業員のwell-being向上による生産性や競争力の向上
-
従業員のスキル・能力の向上による生産性や競争力の向上
-
多様性の豊かな組織であることによる適切な判断、競争力の向上
-
心理的安全性が高く、働きやすい職場環境による生産性や定着率、レピュテーションの向上
-
ダイバーシティ&インクルージョンに関わる様々な制度設計、情報発信、社会的な企業評価等の充実による優秀な人材の獲得
主な取り組み
リスク対応
機会対応
継続的な組織モニタリング(従業員エンゲージメントサーベイの実施等)
◎
◎
企業理念(「愛」「敬」の精神)の浸透
◎
◎
多様な働き方の推進
◎
◎
公正で人的資本戦略に即した人材採用
◎
◎
タレントマネジメント、人材開発の推進
◎
◎
ダイバーシティ&インクルージョンの推進
◎
◎
健康経営の推進
◎
◎
ガバナンス・リスクマネジメントの強化
リスク
-
コーポレート・ガバナンスの欠如による不祥事の発生、競争力の低下、経営の質の低下
-
コンプライアンス違反による訴訟・罰金の増加、レピュテーションの低下
-
情報セキュリティ対策の不備による訴訟・罰金の増加、レピュテーションの低下
-
不十分なリスクマネジメントによる不祥事の発生、業績の悪化、レピュテーションの低下
機会
-
コーポレート・ガバナンスの強化による健全な経営の実施、競争力の向上
-
コンプライアンスの徹底による信頼性・レピュテーションの向上
-
十分な情報セキュリティ対策によるスムーズな事業運営、信頼性・レピュテーションの向上
-
リスクマネジメントの強化による経営の質・競争力・レピュテーションの向上
主な取り組み
リスク対応
機会対応
コーポレート・ガバナンスの強化
◎
○
コンプライアンス・腐敗防止の強化
◎
○
内部通報制度の周知徹底
◎
○
サイバーセキュリティ等の情報セキュリティ対策の徹底
◎
○
リスクマネジメントの強化
◎
○
リスク
- 自社・グループ会社における人権侵害による訴訟のリスク、レピュテーションの低下、生産性の低下
- 拠点等の地域社会における人権侵害による訴訟のリスク、レピュテーションの低下
- 地域社会からの反発による操業の停止、レピュテーションの低下、就業者の不足
- 地域社会の衰退による経済の縮小、就業者の不足、治安の悪化等による操業の停滞・停止
機会
- 人権尊重の企業姿勢・行動によるレピュテーションの向上
- 自社・グループ会社における人権尊重による職場の活性化、生産性の向上
- 地域社会との共生、信頼関係の構築によるスムーズな事業運営
| 主な取り組み | リスク対応 | 機会対応 |
|---|---|---|
| 自社・グループ内の人権DD実施(人権DDデジタルサーベイ) | ◎ | ◎ |
| 自社・グループ内の企業理念の浸透、人権に関する教育の実施 | ◎ | ◎ |
| コンプライアンス・腐敗防止の強化 | ◎ | ○ |
| 内部通報制度の周知徹底 | ◎ | ○ |
| 外部ステークホルダーとのエンゲージメント機会の整備 | ○ | ○ |
| 社会貢献活動の推進 | ○ | ○ |
リスク
- 従業員のwell-being(身体的・精神的・社会的に満足な状態)低下による生産性や競争力の低下
- 従業員のスキル・能力の低下による生産性や競争力の低下
- 多様性の欠如による思い込み・判断ミスの発生、競争力低下
- 心理的安全性が低く、働きづらい職場環境による生産性やレピュテーションの低下、離職者の増加
- ダイバーシティ&インクルージョンに関わる様々な制度設計、情報発信、社会的な企業評価等の不足による優秀な人材の獲得機会の喪失
機会
- 従業員のwell-being向上による生産性や競争力の向上
- 従業員のスキル・能力の向上による生産性や競争力の向上
- 多様性の豊かな組織であることによる適切な判断、競争力の向上
- 心理的安全性が高く、働きやすい職場環境による生産性や定着率、レピュテーションの向上
- ダイバーシティ&インクルージョンに関わる様々な制度設計、情報発信、社会的な企業評価等の充実による優秀な人材の獲得
| 主な取り組み | リスク対応 | 機会対応 |
|---|---|---|
| 継続的な組織モニタリング(従業員エンゲージメントサーベイの実施等) | ◎ | ◎ |
| 企業理念(「愛」「敬」の精神)の浸透 | ◎ | ◎ |
| 多様な働き方の推進 | ◎ | ◎ |
| 公正で人的資本戦略に即した人材採用 | ◎ | ◎ |
| タレントマネジメント、人材開発の推進 | ◎ | ◎ |
| ダイバーシティ&インクルージョンの推進 | ◎ | ◎ |
| 健康経営の推進 | ◎ | ◎ |
ガバナンス・リスクマネジメントの強化
リスク
-
コーポレート・ガバナンスの欠如による不祥事の発生、競争力の低下、経営の質の低下
-
コンプライアンス違反による訴訟・罰金の増加、レピュテーションの低下
-
情報セキュリティ対策の不備による訴訟・罰金の増加、レピュテーションの低下
-
不十分なリスクマネジメントによる不祥事の発生、業績の悪化、レピュテーションの低下
機会
-
コーポレート・ガバナンスの強化による健全な経営の実施、競争力の向上
-
コンプライアンスの徹底による信頼性・レピュテーションの向上
-
十分な情報セキュリティ対策によるスムーズな事業運営、信頼性・レピュテーションの向上
-
リスクマネジメントの強化による経営の質・競争力・レピュテーションの向上
主な取り組み
リスク対応
機会対応
コーポレート・ガバナンスの強化
◎
○
コンプライアンス・腐敗防止の強化
◎
○
内部通報制度の周知徹底
◎
○
サイバーセキュリティ等の情報セキュリティ対策の徹底
◎
○
リスクマネジメントの強化
◎
○
リスク
- コーポレート・ガバナンスの欠如による不祥事の発生、競争力の低下、経営の質の低下
- コンプライアンス違反による訴訟・罰金の増加、レピュテーションの低下
- 情報セキュリティ対策の不備による訴訟・罰金の増加、レピュテーションの低下
- 不十分なリスクマネジメントによる不祥事の発生、業績の悪化、レピュテーションの低下
機会
- コーポレート・ガバナンスの強化による健全な経営の実施、競争力の向上
- コンプライアンスの徹底による信頼性・レピュテーションの向上
- 十分な情報セキュリティ対策によるスムーズな事業運営、信頼性・レピュテーションの向上
- リスクマネジメントの強化による経営の質・競争力・レピュテーションの向上
| 主な取り組み | リスク対応 | 機会対応 |
|---|---|---|
| コーポレート・ガバナンスの強化 | ◎ | ○ |
| コンプライアンス・腐敗防止の強化 | ◎ | ○ |
| 内部通報制度の周知徹底 | ◎ | ○ |
| サイバーセキュリティ等の情報セキュリティ対策の徹底 | ◎ | ○ |
| リスクマネジメントの強化 | ◎ | ○ |
マテリアリティに関わる長期的なビジョン・戦略およびKPI・目標
長期的なビジョン
◆長期目標
GHG排出量(スコープ1,2): 2030年度までに2022年度比42%削減 / 2050年度カーボンニュートラル達成
◆長期的な目指す姿
- 脱炭素社会/循環型社会/豊かな自然資本が実現している社会・地球。
- 人々が人権を尊重され、安全・安心を実感し、各々のwelll-beingが保たれている社会。
- ビジネスパートナーと共創して生み出される、当社の提供する価値が、社会において「なくてはならない価値」として選ばれ、持続的に成長している状態。
- 持続的な成長に欠かせない国内外のすべての従業員が、心身共に健康であり、各々にフィットした働き方・適切な役割でイキイキと働き、well-beingが高い状態。
◆関連するSDGs
戦略およびKPI・目標
長期的なビジョンからバックキャストし、2カテゴリー6つのマテリアリティに沿った2024~2026年度の3ヵ年のKPI・目標を策定しました。| 持続的な価値創出 |
|
|---|
| 戦略 | KPI・目標(2024年4月~2027年3月) | バウンダリー |
|---|---|---|
| 事業活動におけるカーボンニュートラルの達成 | GHG排出量(スコープ1,2)を2022年度比25%削減 | 連結 |
| 事業を通じた地球環境への貢献 | 環境関連ビジネスの売上高1,000億円*1を達成 | 連結 |
| 化学物質規制管理の強化による安全・安心な品質の確保 | 国内外における化学物質規制の動向をタイムリーに把握・共有し、管理体制を強化 | 連結 |
| サプライチェーンマネジメントの強化による調達・供給機能の強靭化 | 責任ある調達に関する当社姿勢を明確にし、社内外に浸透 | 単体 |
| 人権に配慮したサプライチェーンの確立 | 選定した事業について人権DDのサイクル*2をモデルケースとして確立 | 単体 |
-
*1 「サステナビリティ中期計画2026」の最終年度で想定している環境関連ビジネスの分野別比率は以下の通り。
■エネルギー・電力(再生可能エネルギー関連、電池関連など):約70%
■資源・環境(持続可能な原材料、リサイクル、水関連など):約20%
■素材・化学、農業・食料、交通・物流、環境認証 :約10% -
*2 人権DDに関するサイクルとは、「責任ある企業行動のためのOECDデュー・ディリジェンス・ガイダンス」で示されている以下の「デュー・ディリジェンス・プロセス及びこれを支える手段」のこと。
①責任ある企業行動を企業方針および経営システムに組み込む
②企業の事業、サプライチェーンおよびビジネス上の関係における負の影響を特定し、評価する
③負の影響を停止、防止および軽減する
④実施状況および結果を追跡調査する
⑤影響にどのように対処したかを伝える
⑥適切な場合是正措置を行う、または是正のために協力する
| 事業継続の基盤 |
|
|---|
| 戦略 | KPI・目標(2024年4月~2027年3月) | バウンダリー |
|---|---|---|
| 持続的な成長を支える従業員のwell-being(身体的・精神的・社会的に満足な状態)の向上 |
|
連結 |
| 多様な個を最大限に活かすダイバーシティ&インクルージョンの推進 |
|
単体 |
|
連結 | |
| 健康経営の更なる推進 |
|
単体 |
| 人的資本投資への注力 |
|
単体 |
- *3 従業員エンゲージメントサーベイの肯定的回答率とは、従業員による5段階評価(5.とてもそう思う/4.そう思う/3.可もなく不可もなく/2.そう思わない/1.全くそう思わない)のうち、肯定的な回答である5と4の占める割合のこと。
-
*4
精密検査受診率とは、健康診断後の要精密検査受診対象従業員のうち、実際の精密検査受診従業員の割合のこと。
総合健康リスクとは、厚生労働省がストレス評価の方法として提供しているもので、ストレスチェックから得られた「心理的な仕事の負担(量)」「仕事の裁量度」/「上司からの支援度」「同僚からの支援度」の4尺度を用いて算出される、職場の環境が従業員の健康にどの程度影響を与えるかを総合的に評価する指標。全国平均の値を100として計算されており、100を超えると職場の健康リスクが高い状態、下回るとリスクが低い状態と考えられる。当社は現状100を下回る状態。 - *5 教育研修費用は、サステナビリティ>人材育成のページをご参照。