社外取締役鼎談
昨今の厳しい事業環境のなかで、稲畑産業はどのような取り組みをしているのか。経営を客観的な視点から監視・監督する役割が期待されている社外取締役の方々にお話を伺いました。
(本鼎談は2025年5月中旬に実施しました)

取締役 長南 収 (左)
在任期間 :2023年6月~現任
私の役割
日本で、そして中国、東南アジアを中心に健康を支えるサラダの食文化市場をつくり、リードしてきた食品メーカーで、製造部門はじめ営業部門の責任者を長く務めてきました。また、経営者として多様な経験と知識を積み重ねてきましたので、特に、商品のブランディング等を外部的視点から向上させ企業イメージや価値を高めていきたいと考えています。
取締役 萩原 貴子 (中央)
在任期間 :2021年6月~2025年6月
私の役割
長年にわたって製造業やサービス業の組織に関わる人づくりに携わってきたほか、グローバル市場での新規事業創出などについても経験してきました。特に人材開発や組織戦略の立案・推進に長く携わってきたことから、稲畑産業においても“時代の変化に挑戦し続ける人づくり・組織づくり”に貢献していきたいと考えています。
取締役 末川 久幸 (右)
在任期間 :2024年6月~現任
私の役割
創業150年超の化粧品メーカーで事業戦略や経営改革を推進。CSRの側面から社会課題にも取り組み、社内保育所や深刻な肌悩み専門の相談センターの設立を主導。こうした社会とのコミュニケーションによるブランド力の向上に加え、現在取り組んでいる大学での講義や企業研修の経験やノウハウを生かして、当社の人材育成に貢献できればと考えています。
中長期の視点に立った意識改革について
中計2年目を迎えての課題や社内の意識改革についてどう感じていらっしゃいますか?
末川
おっしゃる通りです。これは「商社」と「メーカー」のビジネスに対する姿勢の違いではないかと思います。私はメーカー出身ですので、どちらかというと「選択と集中」で攻めて短期間に答えを出すことを重視していました。しかし、当社は「これを取り扱わなくなれば、世の中が困るので、我々が守っていこう」「他社が止めても残そう」といった利他の姿勢が強いように思います。これは、社是にある「愛」「敬」にも通じる企業風土ではないかと考えていますが、ときには一気に攻めていく姿勢も必要だと思います。
長南
稲畑産業の「ビジョン(目指す姿)」にある「変化への対応」という言葉も、変化を自らつくっていかなければ、後手になってしまうと指摘したことがあります。それに対して経営陣から返ってきたのは、「商社はお客さまのニーズの変化に対応していくことが大切なんだ」ということでした。「なるほど」と思った一方で事業環境が目まぐるしく変わっていくなかでは、変化を起こすことも必要なのではないかとも思います。例えば、食品を扱っている生活産業事業では、研究機関やメーカーとネットワークをつくって食材の新しい冷凍技術を開発するなどの変化を起こすことが、サプライチェーンの革新や新たなビジネスにつながっていくのではないでしょうか。
末川
以前の取締役会で、「昭和っぽい社名を変えてはどうか」という株主の声が紹介されました。これを受け、私たちB to C企業出身の社外取締役は、「海外売上比率が過半を超えた今、海外でも通じやすい社名やブランディングの検討をしてはどうか」と提案しました。しかし「社員から社名変更の意見は出たことがない」との回答で議論は深まりませんでした。社内では当たり前の話でも、外から見る印象は異なります。あくまで一例ですが、未来を見据え、経営陣で丁寧に議論しても良いテーマには私たちをもっと活用いただければと思います。
長南
昔からの社風を分かっている人たちが事業をけん引している間はよいですが、いなくなったときに「稲畑産業の特徴とは何か?強さは何か?」という問いに答えられるのか、長期ビジョンのゴールは決まっているけれど、その達成に向けて商材や人材はどうするのか、中長期で企業ブランドをどう高めていくか、といった観点での議論がまだ弱いと感じます。
萩原
そうした意見は従業員からはなかなか上がってきませんが、稲畑産業は複数の社外取締役から継続的に出てくる意見を真っ向から受け止めてくださっています。だからこそ、我々も大胆な意見や個人的な想いを、取締役会で直接ぶつけることができています。
取締役会における議論のテーマについて
最近は、どのようなことが議論のテーマに上がっていますか?また、今後に向けた課題も教えてください。

“商社らしい
「守りの姿勢」も大事ですが、
厳しい事業環境下では、ときには
「一気に攻めていく姿勢」も重要”
末川 久幸
末川
私は2024年に社外取締役になりました。それまで商社の経験がなく、扱っている商材もよく分かりませんでしたが、丁寧に教えてくださいますし、取締役会での議論を通し、ずいぶん理解が進んできました。日々の業務への我々の提言に対して、きちんと改善がなされていることはありがたいと思っています。
長南
厳しい環境下における現状の課題と今後の計画は報告がなされていますね。ただ、社外取締役である我々は、取締役会だけでなく、現場側の「こういう問題があるから、やろうと思ってもできない」という意見も聞いていますので、経営のあるべき姿と現場の理解とのギャップを埋めて、スムーズに計画が進むよう後押しすることも、我々の役割だと感じています。
萩原
現在、検討されているM&Aなど積極的な姿勢は評価しますが、大事なのはその後のPMI(統合プロセス)です。進捗状況や課題について、我々から問いかける場面がありましたが、そうした外の立場からの直截的な投げかけを通じて、コミュニケーションは深まっていますね。
末川
買収後のハンドリングやプロジェクトマネージメントの面で人が足りていない印象があります。また、当社のIK Valuesという価値観を、買収した会社にどう浸透させていくのかなど、あまり経験値がないことについても道筋を立てておく必要がありますね。
萩原
それと「重要なポジションを担う後継者」をどう育成していくのかというサクセッションプランは、今のところ具体的な進捗という点からはまだ不十分な状態です。ただ、全取締役が参加した人材育成のブレインストーミングで人事担当の方と課題認識などを共有できたのは、よかったですね。人事データベースの構築など、インフラづくりは着実に進めていただいています。
末川
いろんな経営人材をプールして、選抜・育成していくという視点は評価できます。しかし、私たちは残念ながら、そういう経営人材の方々の顔が分かりませんので、例えば、取締役会で何か提案をしてもらったり、食事でもしながら話をして課題感をリサーチしたりする機会があれば良いと思います。
長南
3年、5年先を見据えて次の後継者をどうするかの考え方をそろそろ固めていかなければいけません。性別やプロパーかどうかに関係なく、経営を任せられる人材が選ばれるのが理想ですが、実現の道筋はどうするのか。また、従業員の成長や会社の発展にどうつなげていくかが、次の議論のテーマですね。
萩原
資本市場で問われている資本効率や株価については監査等委員の方が常に厳しくチェックしてくださっていて、執行側も誠意を持って答えています。多彩な監査等委員の方々がいろんな意見や疑問を呈することで、議論が活発に進んでいます。

“経営のあるべき姿と
現場の理解とのギャップを埋めて、
スムーズな計画進捗を
後押ししていきたい”
長南 収
人的資本の強化について
人材の育成強化に関して、重要になってくる視点はどんなことだとお考えでしょうか?
萩原
一昨年、1日かけて中期計画の議論をした際に人事の課題がいろいろと出てきました。そこで今回は先ほども申し上げた全取締役が参加した人材育成のブレインストーミングを丸1日かけてやって、人事の責任者の方、次の世代の事業の責任者の方たちと意見交換をさせていただきました。すぐに結論が出るわけではありませんが、互いにさまざまな課題感を深堀して共有できたのは、良かったと思います。
末川
これからの事業展開を考えると、日本人の従業員も、海外の現地スタッフも、グローバル人材をどう育成していくかは、大きな課題です。もう1つ、萩原さんがいつもおっしゃっていることですが、ダイバーシティだけではなく、多様な個性を生かし従業員がいかに生き生きと働けるかというインクルージョンが重要です。例えば、女性の管理職の比率を上げるだけでなく、どうすれば彼女たちが活躍できるかまで踏み込んで考える必要があると思っています。
萩原
そうですね。男性の育児休暇もただ取得すればいいわけではありません。それによって働き方を変えるという観点が重要で、そこまで議論をもう一歩進めなければならないということに、経営陣は気づきはじめていて、理解がこの4年間でずいぶんと深まってきたと感じています。そして、いよいよ次の時代に向けて、商社ならではの、稲畑産業ならではの強みのようなものを、皆悩み苦しみながら考えていますので、答えが出てくることをとても期待しています。
サステナビリティについて
サステナビリティに関して、社外取締役の方の役割や取り組みの進捗状況を教えてください。
萩原
サステナビリティについては、我々、社外取締役もサステナビリティ委員会のオブザーバーとして、年2回報告の場に出て意見を述べさせていただいています。事務局の方々は非常に優秀で熱意があって、着実に議論がレベルアップしてきています。先日開催されたサステナビリティ委員会では、委員の方だけでなく、社外取締役側からも活発な意見が出て、時間が足りなかったくらいでした。
長南
環境についても、スコープ1から3までのなかで、排出源ごとに温室効果ガスの削減目標を持って進めていただいています。当社は、事業でもリサイクルフィルムなどの環境関連商材も扱っていて、環境ビジネスが収益にもつながっています。しかし、ここで気をつけなければいけないのがコストです。良いことをやっても会社の業績が悪くてはいけません。コストと業績のバランスは大切です。その視点を持ったうえで、新しい技術を積極的に取り入れ、画期的な省エネビジネスなど“商社らしい動き”につなげていってほしいと思います。
末川
そういうことを従業員同士で議論できるようになれば、かならずイノベーションが起きて、成長につながっていくと思います。環境問題やサステナビリティは、誰かがやっている、やってくれているだろうという意識ではなく、従業員一人ひとりが自分ごととして捉えられるような風土の醸成が重要ですが、それはそんなに難しいことではないと思っています。
萩原
課題となったことについては一つひとつ確実に手を打っていることが稲畑産業の特徴であり、強みであると思っています。また、我々社外の取締役も含め、経営陣をしっかり巻き込んで意識啓発をしていこうとしていると感じます。あとは、この流れをどうやって継続してやっていくかです。現在、中途入社の社員がどんどん増えていますが、新しいメンバーと早いスピードでどうやって共有化を進めていくかという知見がまだまだ足りていないと感じます。
長南
もう1つ、今、日本で一番の問題は子どもの問題、すなわち少子化だと私は思っています。その課題を解決し社会に貢献していくために、企業が育児制度を充実させるのはもちろんよいことですが、もっと社会課題としてみんなで考え、解決策を率先して導き出せるようになれば、「本当に良い会社だよね!」となるのではないでしょうか。
萩原
長南さんの考えにとても共感します。そうなるためには、従業員が会社のなかだけではなく、社会にちゃんと目線を向けていくことが必要です。先ほどの話に出たように、女性の管理職・営業職が増えればよいということではなく、女性であっても営業職で活躍できる会社である、社会である、そのことに当社は貢献しているということが、会社の価値にもなりますし、従業員のモチベーションにもなると思います。

“課題に対して、
着実に手を打っていることが、
稲畑産業の特徴であり、強み”
萩原 貴子
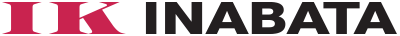



萩原
新しい中期経営計画がスタートして1年が経ちましたが、米国による関税措置の影響など厳しい事業環境のなかでも、確実に数字を出し成長されているので、安心して事業を見ていられますね。一方で、変化に対する大胆さやスピード感については、まだまだ課題があると感じています。例えば、社内の暗黙知によって継続を判断しているビジネスなどは「本当に続けていく必要があるのか」という議論が必要だと思いますね。